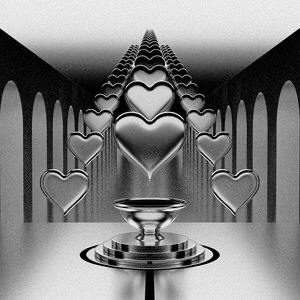■はじめに ビーチ・ハウスはヴィクトリア・ルグランとアレックス・スカリーによって2004年にメリーランド州ボルチモアで結成されたドリーム・ポップ・デュオです。本日2月18日に待望の8thアルバム "Once Twice Melody" がリリースされました。この記事では、ニュー・アルバムのリリースを記念して、2006年にセルフタイトルのデビュー・アルバムをリリースして以来7枚のアルバムを発表してきた彼らのこれまでの足跡を「全オリジナルアルバムレビュー」という形で振り返ったみたいと思います。 オルガンとギターとドラムマシーンというミニマルな構成からスタートし、やがてはドリーム・ポップと呼ばれる一大ジャンルの代表的バンドとなったビーチ・ハウスの音楽は、この18年間で音楽性がガラリと変わったことはなく、ある意味では金太郎飴のようにどこを切っても同じような断面が見えてくるタイプの音楽と言えるかもしれません。しかし、初作から最新作まで順を追ってアルバムを聴いていくと、確固とした軸を持ちながら常に新しいことに挑戦し着実に蓄積を重ねて音楽性を高めてきた彼らの誠実な姿勢が本当によくわかります。 もし「好きなアルバムはあるけど全部は聴いてない」という方や「新しいアルバムを聴いてビーチ・ハウスに興味を持った」という方がいましたら、是非1stアルバムからじっくりと聴いてみてほしいなと思います。アルバムをリリースし、ツアーを行い、そのフィードバックをまた次の作品に反映させる、というサイクルを堅実に続けてリリースされてきた作品を順番に追うことで、彼らの螺旋状の進化の過程がよりスリリングに味わえるはずです。
◻️Beach House (ビーチ・ハウス) オリジナル・アルバム全作レビュー
アレックス・スカリーの自宅の地下室で4トラックレコーダーで2日間で録音された2006年リリースのデビュー・アルバム。収録曲の ‘Master of None’ は、後にザ・ウィークエンドのデビュー・ミックステープに収録の楽曲 ‘The Party & The After Party’ (2011) にサンプリングされ、ミランダ・ジュライの映画 “The Future” (2011) に使用された。
“Love you all the time / Even though you’re not mine (いつでもあなたを愛してる あなたは私のものでないけれど)”という直接的に愛の不全を綴った歌い出しで始まるオープニング・トラック ‘Saltwater’ から、アルバムのムードは一貫して甘く、苦く、気怠い。時にクラシカルなフレーズを奏でつつ多彩な音色を駆使しながらアトモスフェリックな効果を生み出すオルガン、幽霊のように漂う控えめなギター、それらが簡素なリズムトラックの上でユニゾンとなって融け合うサウンドは、後のビーチ・ハウスの原型を感じさせ、じわじわと空間を温かな水で包み込んでいくような心地良いムードを醸成していく。晩夏の誰もいない日没前のビーチ、真夜中に一部屋だけ明かりの灯ったベッドルーム、あるいは静かな海の底。想起するイメージはひどく孤独であるが、同時にどこか胎内的な温もりを感じさせるものだ。
“Teen Dream” 以降の作品を聴いてビーチ・ハウスを聴くようになった人はこのアルバムのぼんやりとした雰囲気に少し戸惑いを憶えるかもしれない。メロディーはあまりにも朧気だし、ボーカルは魅力的ではあるがまだまだ頼りなく、展開も単調でドラマチックさに欠ける。にもかかわらず、得てして多くのバンドやアーティストの1stアルバムがそうであるように、ビーチ・ハウスのこのデビュー・アルバムも以降のアルバムでは聴くことのできない特別な輝きを放っている。志の高さと技術の未熟さ、あるいは録音環境の貧しさが故に表現の純度が高さが際立ったダイヤモンドの原石のような愛すべきデビュー・アルバム。
デビュー・アルバムから2年のスパンでのリリースとなった2008年の2ndアルバム。基本的にはギターとオルガンと最小限のドラムの親密なアンサンブルでメランコリックな世界を構築する前作の手法を引き継いだ作品だが、あらゆる面において進化の過程を聴き取ることができるアルバムだ。
まず、ヴィクトリア・ルグランのボーカルが本作において格段の進歩を遂げている。デビュー作におけるルグランのボーカルは、魅力的ではあるもののまだどこか頼りなく、線の細さを感じさせるものだったが、本作において、ニコを思わせるルグランの低くハスキーなボーカルは、憂いを感じさせるときもあれば、ソウルシンガーのような力強さを感じさせるときもあり、芯がありながらも表情の豊かさを感じさせる。また、前作においては控えめだったアレックス・スカリーのギタープレイも本作においてはよく目立っている。侘しさを喚起するギターのテーマが印象的な ‘Gila’、ビーチ・ハウスの代名詞と言えるようなトレモロ・ギターが曲を盛り立てる ‘Heart of Chambers’ など、ギターが核を担う楽曲が増え、それに比例するようにアレンジの幅が広がり、楽曲に彩りを与えている。
アルバムのムードとしてはどこかリラックスした印象も受ける作品で、楽曲の質と聴き心地の良さで何度も繰り返し聴かせるだけの力のある作品となっている。個人的なハイライトは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを思わせるダウナーな ‘Some Thing Last a Long Time’(ダニエル・ジョンストンのカバー)からアルバム中で最も高揚感を感じさせる ‘Astronaut’ への流れ。曲と曲の繋がりで視界が開けるような「流れ」を感じさせてくれる瞬間がたまらなく心地良い。次作以降ドリーム・ポップの旗手として飛躍的な進化を遂げるビーチ・ハウスだが、ボルチモアという港町出身のこのデュオにおいて、最も「ビーチ感」のある作品であるようにも感じられる。
前作リリース後の大規模なツアー中にアイデアとエネルギーを貯め込み、「ツアーが終わる頃には、早く家に帰って次のアルバムに取りかかりたいと思うようになっていた」とスカリーが語る2010年リリースの3rdアルバムは、その言葉通り、多くのライブを経た2人のプレイヤーとして、ボーカリストとしての進化が明確に刻み込まれた作品となっている。
とりわけ、前作から楽曲の核を担うことが多くなったスカリーのギタープレイは、本作において飛躍的な進化を遂げた。オープニング・トラックの ‘Zebra’ における美しいギターのテーマはそのまま楽曲の中心を担い、四つ打ちのドラムと荘厳なコーラス、ルグランのエレガントで滋味深いボーカルが加わって、静かな高揚感のある名曲に仕立て上げられている。他にも ‘Norway’ における幻想的で陶酔感のあるギタープレイや ‘100 Mile Stereo’ におけるドラマチックに曲を盛り立てるトレモロ・ギターなど、特筆すべき名演は多い。ソングライティングの面に目を向けてみても、以前の作品に比べてメロディーは格段に輪郭が鮮明になり、起伏に富んだ展開を持つ各楽曲は端的に言ってクオリティーが飛躍的に向上している。また、サウンドや楽曲が洗練されることに比例して、ルグランのボーカルも一層魅力的に感じられ、清廉なサウンドとエレガントでワイルドなボーカルのコントラストがこのデュオの肝であることも強く感じさせられる。
ビルボードチャートの43位にランクインし、数多くのメディアの年間ベスト上位に選出された出世作であり、ピッチフォークの “The 30 Best Dream Pop Albums” の3位にランクインしたドリームポップを代表する作品。プロデュース / エンジニアには、TV・オン・ザ・レディオやヤー・ヤー・ヤーズ、キャス・マックムースなどとの仕事で知られるクリス・コーディーが起用され、本作から6thアルバムまでタッグを組むこととなる。
前作 “Teen Dream” の成功からまたしても2年のスパンで届けられた2012年の4thアルバム。前作に引き続きクリス・コーディーが共同プロデュース / エンジニアを務めた。ピッチフォークではビーチ・ハウスのカタログ中で最高スコアの「9.1」を獲得し、ビルボードチャートでは7位にランクイン。商業的にも批評的にも現時点で最も大きな成功を収めた作品と言えるだろう。
まさに花開くように高らかなギターとキーボードのユニゾンが響くオープニング・トラックの ‘Myth’ から、軽やかなドラムが曲を牽引するミドルテンポの ‘Wild’ へと繋がる冒頭の2曲、あるいはビーチ・ハウス史上最もアグレッシブで推進力のある ‘New Year’、あまりに崇高でドリーミーな ‘Wishes’、アルバムの締めくくりに相応しい壮大な ‘Irene’ など、どの曲どの瞬間を切り取ってもバンドが描いていた音楽の青写真が実現したと確信するに足る美しさがある。”Teen Dream” で到達したギターとオルガンの絡みは、もはや完璧に同化しているかのように寸分の狂いもなく調和しているように感じられ、全ての中心にあるルグランのボーカルは一層深みが増し神々しさすら感じさせる。前作にも参加していたドラマーのダニエル・フランツが本作においては全曲で生のドラムとパーカッションを叩いていることが大きな役割を果たしており、このアルバムが持つ躍動感を支えている。
前作でひとつの完成形を提示したビーチ・ハウスだが、そこからさらに先に進んでダイナミズムをモノにした本作は、どんなに大きなステージで演奏されても遜色のないような壮大さを纏っている。あの1stアルバムから本質的にはブレることなく蓄積を重ねてここまでのスケールに到達したことに感慨深さもあり、その到達した地平の高さに何度聴いても感動させられる。名盤と呼ぶに相応しいオーラのある作品だ。
デビュー作から常に2年のスパンでアルバムをリリースしてきたビーチ・ハウスが初めて3年の期間を空けてリリースした2015年の5thアルバム(もっとも彼らはこの年にもう1枚アルバムをリリースすることになる)。引き続きクリス・コーディーが共同プロデュース / ミキシングを担当した。
本作に関する公式のステイトメントでは「”Teen Dream” と “Bloom” の成功はバンドを大きなステージ(ラウドでアグレッシブな場所)に導いたが、それは自分たちを自然な傾向から遠い場所へと追いやった。本作では、自分たちが存在する商業的な背景を完全に無視して、自分たちを進化させ続けている」といったことが記されている。また、「生ドラムの役割をはるかに少なくし、メロディーといくつかの楽器を中心に構成したシンプリシティーへの回帰を示した」ともある。要するに “Bloom” で到達した高みから下りて今一度自分たちの足元を見つめ直して製作した作品ということだろう。ダイナミックなアレンジが施され荘厳な雰囲気を纏っていた “Bloom” に比べると落ち着いた楽曲で構成されたアルバムとなっているが、本作リリース時のインタビューでルグランが「何も後ろ向きに進むっていうことではなくて、私たちは今も前に進み続けている」と語っているように、決して原点回帰を志していたわけではない。先行シングルだった ‘Sparks’ の閃光のようなディストーションギターが前面に出たこれまでにない攻めた楽曲や、オールディーズを思わせるような語りのパートをイントロや間奏で聴かせる ‘PPP’(曲タイトルは3連符を使用したリズムと関係があるのかもしれない)、クワイア・コーラスを取り入れた ‘Days of Candy’ など、新しい手法を聴くこともできる。
本作のレコードとCDのジャケットはベルベット生地があしらわれた仕様だったが、アルバムの質感も彼らのディスコグラフィーの中でも特に気品のある作品であると感じられる。これまでの歩みの中で培ってきた方法を取捨選択しながら自分たちのムードに忠実に完成させたアルバムだと言えるだろう。
“Depression Cherry” の僅か2ヶ月後にリリースされた6thアルバム。録音は “Depression Cherry” と同時期ではあるものの、それぞれを繋がりのない作品と見るべきだということで別々の作品としてリリースとなったようだ。アートワークは1950年代の終わりに撮影されたルグランの母の写真が採用されている。
シューゲイザーライクな音の重なりを聴かせるオープニング・トラックの ‘Majorette’ からスロウなテンポでストロークされる歪んだギターに妖艶なボーカルが乗る ‘One Thing’、重厚なオルガンとサイケデリックなギターが重なる’The Traveller’、シンフォニックなキーボードとギターのユニゾンが繰り返される前半からディストーション・ギターのギターソロへと雪崩れ込む ‘Elegy to the Void’ など、随所に効果的に使われるディストーションが耳を惹く。前作に比べるとメロディーが立っていてキャッチーなようにも聴こえるのだが、それ以上にある種の空虚さが全体を支配していて、”Bloom” が天上から降り注ぐ光のような音楽であったとすれば、本作は言わば冥界からの音楽のようで、クロージング・トラックの ‘Somewhere Tonight’ の不穏さでその思いが強くさせられる。
ビーチ・ハウスのディスコグラフィーの中では、”Depression Cherry” と並んで、”Bloom” と “7” の間に挟まれた過渡期のアルバムという位置付けになる作品ではあるが、この作品の纏う空虚さに個人的んは強く惹かれる。
前作 “Thank You Lucky Stars” の後、コンピレーション “B-Sides and Rarities” を挟んでリリースされた2018年の7thアルバム。”Teen Dream” からの共同プロデューサーだったクリス・コーディーとのタッグを解消し、新たにスペースメン3のソニック・ブームを共同プロデューサーに迎えて制作された(プロデューサーとしてクレジットされているが、「”7″には、伝統的な意味でのプロデューサーがいない」とも述べられている)。「若返りと再生」を目標とし、ライブでの再現性という制限を取り払い、自由な発想で作曲された楽曲を新たに作ったホームスタジオでアイデアが新鮮なうちにレコーディングをする、という手法で制作された本作は、ある種の閉塞感があった前作からの流れを見事に打破したリスタートの作品である。
ドラムのフィルインから幕を開けるオープニング・トラック ‘Dark Spring’ の重厚な音の重なりはシューゲイザー的というよりはシューゲイザーそのものを思わせ、スカリーのコーラスはコーラスというよりルグランとのツイン・ボーカルに近い。かつてないほどアグレッシヴでスピード感のあるこの曲からシームレスにスロウテンポの2曲目 ‘Pay No Mind’ に繋がる流れは夜空を走るジェットコースターに乗っているような高揚感と煌めきを感じさせる。教会音楽のように荘厳な ‘L’Inconnue’、ビーチ・ハウスらしいメランコリアを聴かせる ‘Drunk in LA’、ドリーミーなコーラスの重なりを聴かせるスロウな前半からモータリックなビートが駆動する後半に雪崩れ込む ‘Dive’、ミステリアスなムードを醸し出す ‘Black Car’、シンプルなコード進行がデザートのように甘い多幸感をもたらす ‘Woo’ など、その後に続く楽曲も全11曲どこを切り取っても隙がなく、その夜間飛行のような感覚は最後まで持続する。音の重なりやコーラスワークは以前にも増して重層的で重厚感があるにも関わらず、それらが緻密に配置されたサウンド・プロダクションはこのアルバムに瑞々しさを与え、どこか軽やかさすら感じさせる作品に仕上げている。
何かがガラリと変わったわけではなく、ここで鳴っているのは紛れもなくビーチ・ハウスの音楽である。しかし、常に以前の自分たちの音楽とは「似て非なるもの」を作り上げてきたこのデュオの真髄を聴かせるように新鮮な驚きと完成度の高さを誇る本作は、ビーチ・ハウスが新たな高みに到達したことを感じさせるに十分な強度を持つアルバムだ。
under construction…